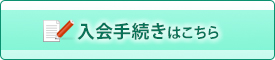会員からのメッセージ
■ 研究の現場から
長い人生だし、新しい夢を追ってみてもいいんじゃない?
椛島 健治(京都大学)

おそらく多くの方は、研究は堅苦しいもので、自分とはあまり縁がないと思っているのではないでしょうか?そして、一流の医師になるためには、臨床に打ち込むことが一番であると考えていませんか?
私たちは、苦しむ患者さんを救いたいという思いをもって医師の道に進んだ訳ですが、実際の医療現場はわからないことだらけで治療法も限られているという現実に直面します。
医師になるまでに私たちが行ってきた勉強は、ページをめくれば答えが載っているような問題集に頼ってきましたが、これから私たちが直面する問題には、答えがあるのかどうかすらわかりません。また、医学の進歩と共に、生物学的製剤などの新たな薬剤も導入されてきています。各対象疾患の病態や薬剤の作用機序を正しく理解しなければ、効果の判定や副作用の予想が難しいという時代に突入しました。
そうなると、医学の真理や高度な医療を追求する術は、臨床だけではなくなります。また、大量の情報が溢れる中、各情報の信憑を正しく判断する審美眼も必要になります。それらの実現のためには「サイエンス(研究)を経験することで養われる効用」を無視できなくなりました。
そしてサイエンスは一部の人のためにのみ存在するのではありません。子供の目をみると好奇心に満ちあふれています。ところが私たちはいつしかその気持ちを失ってきました。一方、なんとか患者さんを助けたいと思って臨床をやっていると、「もしかしたらこの薬が効くかもしれない」とか、「この疾患の病態はこういうことかも知れない」などという思いがわき出してくることがあると思います。その思いは子供の好奇心の目と通じるものがあります。臨床から生まれてくる自分の疑問を私たちはもっと大切にするべきではないでしょうか?
たしかにかつて(10年以上前)の研究は、手技の習得が大変でした。しかし今は、多くの方法が簡略化され、研究というものがとても身近なものとなっています。これからのサイエンスは、どのような疑問をもつのかがより重要となります。どういうわけか、皮膚科は大学を越えた繋がりが密で風通しがいいのが特徴です。ですから、どの大学の医局に所属しようが、解決に向けたチャンスは必ず存在します。
研究は登山のようなもので、天気が悪いときは頂上が見えませんが、それでもこつこつと足を前に進めます。それにルートは一つとは限りません。時に道に迷ったり、雷雨に見舞われたりする事もありますが、頂上に着いたときの爽快感は、登った人にしかわかりません。
皮膚は、サイエンスの対象として魅力に満ちあふれています。そもそも私たちは、人間をみるときに、実は皮膚をみているのです。「落ち込んでいる」とか「嬉しそう」といった表現も皮膚を介して行っています。従って、皮膚は、我々の好奇心や疑問の直接の対象物だと言えます。自分の肌を30分でもいいのでじっと眺めてみてください。シミ、シワ、外傷後の瘢痕、血管腫などの自分の人生が刻み込まれています。
医者としての人生は約40年もあります。その一部の期間をサイエンスに身を置くことは、残りの医師としての考え方の多様性を拡大すると確信しています。
■ 臨床の現場から
皮膚科の守備範囲は広い!
五十嵐 敦之(NTT東日本関東病院)

「皮膚は内臓の鏡」という言葉を皆さんどこかで耳にしたことがあるかと思います。実際、皮膚症状から糖尿病などの内分泌疾患や膠原病、血液疾患、ひいては内臓悪性腫瘍などが発見されることは決してめずらしくはありません。医学生時代、先輩皮膚科医から聞いた「皮膚科医は手のひらを見ただけで全身性エリテマトーデスを診断できる」という一言に驚きと懐疑心を抱いた記憶がありますが、皮膚科を専攻してきた半生を振り返ってみて、この言葉は正しいと断言できます。手間のかかる検査を経ずに皮疹を一目見ただけで診断でき、ひいては患者さんの生活歴までも類推できるところが皮膚科の醍醐味のひとつであると感じています。
皮膚科の取り扱う疾患は接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、ざ瘡、真菌症、乾癬はもとより、膠原病や水疱症などの自己免疫疾患、さらに皮膚腫瘍や母斑症、熱傷などの外科的治療を要する疾患まで多岐にわたり、守備範囲が広いのが皮膚科の特徴です。最近では下肢静脈瘤を扱う施設も増えつつあります。皮膚科は内科的なことも外科的なこともできる誠にやりがいの多い診療科であるといえます。このように広い分野を扱う皮膚科の中で自分の興味が湧く、専門として進みたい領域は必ず見つかると思います。
将来は研究職を、と考えている方もおられると思います。そこで申し上げたいのは、研究の道に進むとしても臨床経験を積んでおくことがその後のキャリアアップにつながるという点です。研究で大切なのは真実の解明とともに診断法や治療法の開発など臨床現場へのフィートバックと考えますが、そのような研究が行えるようになるためには臨床を良く知っておかなければなりません。臨床を経験し現場でのニーズがどういうところにあるのかを知ることによってこそ、研究のアイデアも浮かぶというものです。
また、いわゆるcommon diseaseを誤診しないことは大変重要ですが、これは結構難しいことであると日々思っています。湿疹ひとつとっても臨床像に幅がありますから、標準像からどの程度かけ離れているのか、多くの症例を経験して理解しておくことが正しい診断を下すためには必要です。さらには遭遇する疾患を一つ一つしっかりと学習しつくして自分のものとし、次にその疾患をみたときに標準レベルの対処ができるようにしておくことも大切です。臨床ができればこの道はいくらでも生きていけます。
いっしょに皮膚科の道を歩んでみませんか?
※インタビュー内容、所属は令和3年当時のものです。