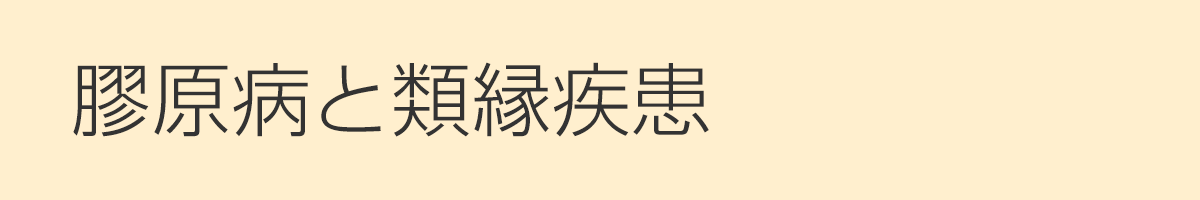Q5好酸球性筋膜炎はどのように診断しますか。
診断に必要な検査として、一般に皮膚生検、画像検査、それから血液検査があげられます。
- 皮膚生検:いわゆる組織検査のことで、硬くなった皮膚の一部に麻酔の注射をして、2~3cmの大きさで切開し、皮膚の下の脂肪、さらには筋膜までを切り取り、筋膜の変化を顕微鏡で確認することで好酸球性筋膜炎を診断することができます。好酸球による炎症が特徴ですが、前述のように好酸球がはっきりしないことも多いです。小さな手術のようなものなので患者さんの負担が大きいですが、最も直接的で重要な検査です。
- 画像検査:核磁気共鳴画像(MRI)が筋膜の変化の確認や病気の勢い、さらには治療効果の判定に用いられます。患者さんの負担は比較的少ないですが、生検ほど細かい変化は分からないため、補助的な検査として使われることが多いです。
- 血液検査:血液でも好酸球の数が増加していることが多いですが、やはり全ての患者さんにみられる訳ではありません。そのほか、血清アルドラーゼ値、IgG値や可溶性IL-2受容体値などの筋肉や免疫に関わる検査項目も、特に重症の患者さんで上昇しやすいです。ただ、これらの異常は他の病気でもよくみられるので、それだけで好酸球性筋膜炎と診断できるわけではありません。
さらに好酸球性筋膜炎と診断された場合、他の膠原病(シェーグレン症候群や関節リウマチなど)や血液の病気(白血病・リンパ腫など)を合併することがあるので、それらの病気がないかどうかも検査することが多いです。