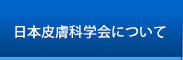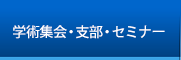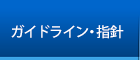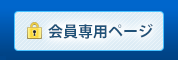会員の皆様へ
「局所皮膚適用製剤の後発医薬品及び剤形追加のための生物学的同等性試験ガイドライン」の一部改正について
2025年04月03日
日本皮膚科学会会員の皆様へ
この度,厚生労働省から「局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学的同等性試験ガイドライン」
及び「局所皮膚適用製剤の剤形追加のための生物学的同等性試験ガイドライン」が改正・発出されました
(令和7年3月31日 医薬薬審発0331 第7号).
また,各ガイドラインにあわせて質疑応答集(Q&A)も改正・発出されました(令和7年3月31日事務連絡).
主な改正は下記の通りです.
- 本ガイドラインは局所皮膚適用製剤を対象としたものであり,軟膏剤,クリーム剤,ゲル剤,パップ剤,テープ剤,ローション剤,外用エアゾール剤,ポンプスプレー剤,外用散剤,リニメント剤が各々異なる剤形として取り扱われること.
- これまで多くの実施例がある皮膚薬物動態学的試験については,上述の剤形区分が異なる,もしくは同じ剤形区分でも基剤の性状※)が異なる製剤間では,健常皮膚において同等性が示される場合でも
病態皮膚で有効成分の移行に差が生じ,治療学的な差異につながる可能性が否定できないことから,臨床試験による同等性評価が必要であるとされたこと. - 皮膚薬物動態学的試験については,試験結果にばらつきを生じる要因として「塗布量」,「角層回収前に皮膚表面に残る製剤の除去方法」,「角層の回収方法」等が示され,これに関する最適化のための方策が盛り込まれたこと.
- 治療学的同等性が厳密に評価されるべき医薬品として免疫抑制剤、作用強度の強いステロイド剤,
レチノイド,抗がん剤,クロラムフェニコール,カルシニューリン阻害剤,JAK阻害剤,免疫調整剤
等が示され,これらについては患者を対象に薬理効果又は臨床効果を指標として統計学的に同等性を評価する検証的な臨床試験を基本とすること. - それ以外の医薬品においては剤形区分が同じで基剤の性状も同じ場合は,生物学的同等性の評価法として有効成分の特性に合わせて皮膚薬物動態学的試験を選択することができること.
一方,剤形区分が異なる場合,又は同じ剤形区分で基剤の性状が異なる場合には,生物学的同等性評価において患者を対象に薬理効果又は臨床効果を指標とした臨床試験の実施が必要であること.
※)油性,水性,乳剤性(W/O 型、O/W型)など
詳細は下記リンクよりご確認ください。
「局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学的同等性試験ガイドライン」等の
一部改正について(PDF/519KB)
「局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学的同等性試験ガイドラインに関する
質疑応答集(Q&A)について」等の一部改正について(PDF/634KB)
2025年4月3日
公益社団法人 日本皮膚科学会