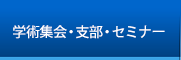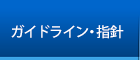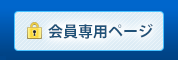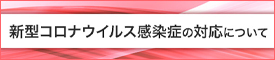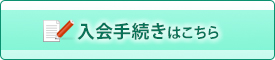沿革
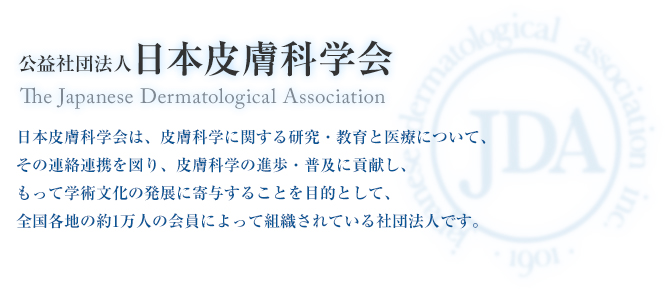
20世紀の軌跡

日本皮膚科学会は、明治33年(1900年)12月、東京帝國大學教授土肥慶蔵博士の提唱により創立されました。翌34年(1901年)4月、第1回総会が開催され、この年、現在の『日本皮膚科学会雑誌』(初刊は「皮膚病學及泌尿器病學雑誌」)が創刊されています。爾来100年、この20世紀に、学会は、皮膚科の研究・教育と診療に真摯な努力を重ね、今日の皮膚科学の進展と皮膚科診療システムの形成等を図ってきました。この間には、湿疹、皮膚炎、アトピー性皮膚炎、皮膚悪性腫瘍などの診断・治療について多くの寄与をしてきたことはもとより、我が国におけるハンセン病や性感染症(梅毒等)などの治療と撲滅に多大な貢献をしています。
昭和49年(1974年)からは、国民生活に影響する難病対策のため、皮膚科医を中心として「研究班」を設け、強皮症・皮膚筋炎、皮膚結合組織疾患、自己免疫疾患、表皮水疱症、神経皮膚症候群など幅広い領域にわたる研究に取り組み、これらの診断基準・治療ガイドライン等を作成するなど、顕著な成果を挙げています。このような実績を踏まえ、昭和57年(1982年)には、東京において第16回「国際皮膚科学会」を開催し、我が国は他の先進諸国とともに、世界の皮膚科学会の中で主導的な役割を果たすようになってきました。現在、多くの会員が諸外国の皮膚科学会に参加しています。世界皮膚科学会連合と協力し、アフリカのタンザニアでの皮膚科医研修支援活動にも参加しています。JICAの活動による開発途上国の皮膚科医育成事業にも協力しています。更には、会員の中から欧米6か国の皮膚科専門学術雑誌11誌の編集委員を輩出するなど、会員の活動は、世界各地に広がってきました。また、一方では、「ひふの日」の事業にみられるように、広く国民に対して皮膚疾患に関する正しい認識の啓発に努める会員の活動も盛んです。このように、日本皮膚科学会は、国の内・外に"開かれた学会"となっています。
21世紀に向けて
21世紀、この学会の果たすべき役割は、ますます高まってくると考えられます。たとえば、地球的な規模で進んでいる生活環境の変化等に関連づけられる諸疾患の原因究明や医療体制の充実などが急がれます。わけても、今や多くの国民が関心を持つようになったアトピー性皮膚炎の診断に関しては、学会で治療ガイドラインを作成したところですが、加えて、新しい治療薬の開発等に国民の期待が集まっています。また、遺伝子レベルでの病態解明と治療の開発についても成果が積まれており、今後ますます発展することと考えられます。このような「時代の課題」はまだまだ多く、21世紀も、皮膚科学は人類の健康としあわせのため、たゆみなく進展し続けることでしょう。