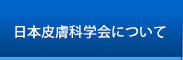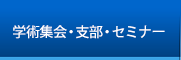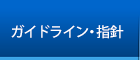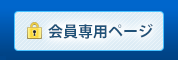会員の皆様へ
皮膚科診療における遠隔医療の位置付けについて
11月2日の理事会において、標記につき審議し下記のように決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、第118回総会において、皮膚科診療における遠隔診療についてのシンポジウムも開催予定としております。
皮膚科診療における遠隔医療の位置付け
近年の情報通信技術の進展に伴い、情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔医療」)が普及してきている。遠隔医療は大別すると、医師が遠隔地の患者を情報通信機器を通して診療する医師―患者間(Doctor to Patient (DtoP))と専門医が非専門医を支援する医師―医師間(Doctor to Doctor (DtoD))に分けられる。さらにDtoPは、患者の診察及びその診断結果の伝達や処方等の診療行為を行うオンライン診療と患者の診察を行い、疑われる疾患等を判断して受診すべき適切な診療科を選択するオンライン受診勧奨に分けられる。皮膚疾患の診断においては、肉眼的に観察された皮膚所見や近年導入されたダーモスコーピーを用いた拡大所見が重要な役割を果たす。またこれらの情報は、画像情報として情報通信機器を用いて医師間、医師患者間で共有することは比較的容易である。
しかし一方、皮膚科クリニック患者の10%以上を占める足白癬、爪白癬(水虫)の診断には、皮膚表面の角層や爪の内の糸状菌(水虫菌)の顕微鏡を用いた確認が必須であり、また皮膚腫瘍や多くの炎症性皮膚疾患の診断においては、皮膚に直接触れ周囲の皮膚との硬さや弾力性の違いを調べる触診も不可欠である。
したがって、皮膚疾患診療における安易な遠隔診療は誤診や重大な疾患の見落としなどの危険性を含んでいる。平成30年3月に厚生労働省から公表された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」においては、そもそも遠隔医療がビデオなどを用いたリアルタイムによる行為と定義されており、画像と問診のみの情報に基づく医療行為は、オンライン診療、オンライン受診勧奨のいずれにも含まれない。
以上を鑑みて、日本皮膚科学会、日本臨床皮膚科医会としては、皮膚疾患のDtoP遠隔診療においてはオンライン受診勧奨に留めるべきと考えている