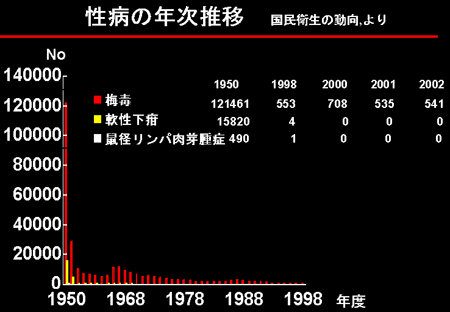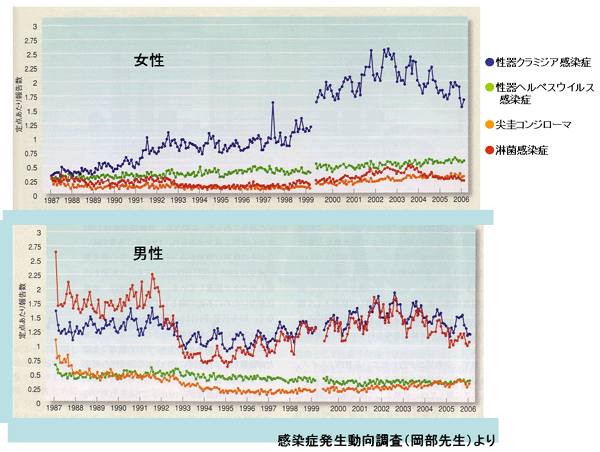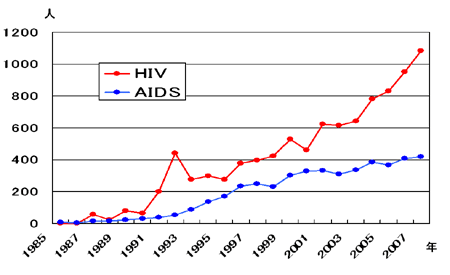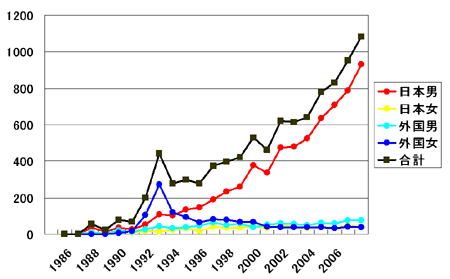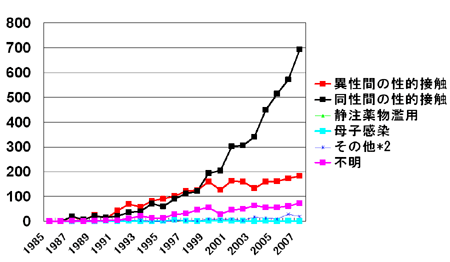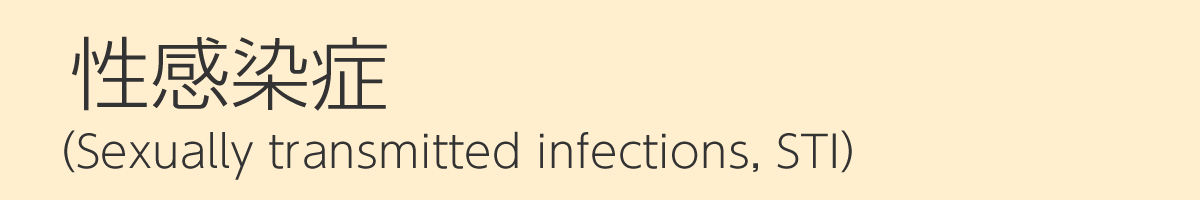Q5どの位流行していますか?
性病4疾患のうち、梅毒、軟性下疳、鼠径リンパ肉芽腫症を皮膚科領域で扱っていましたが、図1の如くこの3疾患はペニシリンなどの抗菌薬の開発により現在激減しております。9県下の産婦人科、泌尿器科、皮膚科、性病科の全医療施設11,853のアンケートに基づく性感染症サーベイランス研究班の調査(6月と11月の2カ月間の調査)によると本邦における性感染症は2001年度において性器クラミジア感染症、非淋菌・非クラミジア性性器炎、淋菌感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、トリコモナス症、梅毒の順に多くみられています。図2に性器クラミジア感染症、淋菌感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマの年次推移を示します。性器クラミジア感染症、淋菌感染症は2002年をピークに減少してきておりますが、性器ヘルペスウイルスは横這い状態でありますが、尖圭コンジローマは若干上昇してきております。感染症動向調査によると梅毒は一時激減しましたが、最近やや増加し、年間600人程度が罹患しています。HIV感染者の約6~7割が梅毒の既往があり、一方抗トレポネーマ抗体陽性者の半分はHIV陽性であるといわれています。HIV感染者が年々増加している現在、梅毒はもっと増加していると考えられます。一方鼠径リンパ肉芽腫症(第四性病)、軟性下疳、鼠径肉芽腫症は日本では非常に稀な疾患となり、1998年度は梅毒553例に対して、軟性下疳4例、鼠径リンパ肉芽腫症1例であり、その後後者2疾患は報告されていませんが、性感染症サーベイランス研究班による2001年度の2カ月間の調査では軟性下疳11例報告されています。
HIV感染者の報告数は、厚生労働省エイズ動向委員会によると平成8(1996)年以降増加が続き、平成19(2007)年は1082件と引き続き過去最高の報告数となりました(図3)。
日本国籍例は969件で、このうち男性が931件と大半を占め、前年より144件増加しました。日本国籍女性例は38件で前年より11件少ない。外国国籍例は113件で、このうち男性が76件、女性が37件で、経年変化はほぼ横這いの状況にあります(図4)。
感染経路別にみると初期は血液製剤による感染が多かったのですが、男性同性間の性的接触が増加傾向にあります。HIV感染例のうち、男性同性間の性的接触による感染は15~24歳の年齢層では75.4%、25~34歳では78.6%、35~49歳では71.2%を占め、50歳以上でも37.7%と異性間の性的接触(35.8%)を超える割合であります。
わが国におけるHIV感染は、これまでの東京を中心とする関東地域の流行に加え、地方大都市においても感染拡大の傾向がみられ、静脈注射薬物濫用、母子感染によるものは少なく、性的接触によるものを中心として拡大しつつあります(図5)。
従って厚生労働省エイズ動向委員会は特に、男性の同性間性的接触による感染に対しては、外国国籍者も含め、積極的な予防施策が必要であり、異性間の性的接触に対しては、男性のみならず女性、特に若年層への重点的な啓発普及が重要であると警告を発しております。