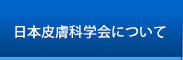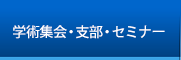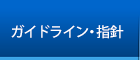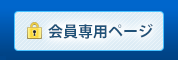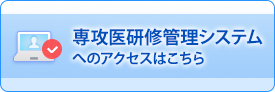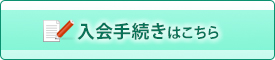日本皮膚科学会認定皮膚科専門医制度の手引き
(平成2年3月改正)
(平成7年7月改正)
(平成15年5月改正)
(平成18年6月改正)
(平成20年4月改正)
(平成29年12月改正)
(平成30年2月改正)
(令和1年6月改正)
(令和2年6月改正)
1.はじめに
皮膚科学会が専門医制度を施行したのは,比較的早く,昭和41年の発足でした.その後,様々な変遷を経て,現行の専門医制度が施行されています.ここでは,まず,他の学会の制度とレベルを揃えることに努め,医療行政の中に専門医制度が取り入れられる日が来ても,ただちに参加出来る体制を配慮してあります.特に,専門医の資格を得た後も,自己研修を義務付けて,医学の進歩に遅れない努力を要求しています.さらに,特に重要な点は,専門医とは何かという概念を,研修目標と研修内容によって具体的に示したことです.この結果,高い専門性を持った皮膚科医が生まれるようになりました.
さて,平成16年から,初期研修に伴うスーパーローテートが医学部卒業後2年間義務づけられることになりました.これに伴い,従来の規則,施行細則,研修目標と内容など,多くの点で変更が必要となりました.研修内容に関しては,現行のものは,一般医学と皮膚科に分けて記述してあります.しかし,一般医学については,スーパーローテートでほとんどの部分を研修するため,この部分の記載内容の変更が大きく変わっております.皮膚科の部分に関しては,ほとんどの部分は従来のものを踏襲しているものの,いくつかの変更が加えられています.また,学習方略に関しては,医学知識の急激な進歩,情報量の著しい増加とその獲得手段の多様化を考慮し,すべて削除いたしました.医学の基礎知識の上に立ったさらに専門性の高い皮膚科医師をと願って,諸規則,研修内容を新たに作成しました.なお,皮膚科研修カリキュラムと実際の研修を充実させるために平成20年より,「主研修施設」を設置し,さらに平成21年度の入会者より申請資格は主研修施設での計1年以上の研修を要することになります.会員各位のご理解とご協力をお願いする次第です.
なお,この手引きは,規則や施行細則を分かりやすく説明して,会員各位の実際の手続きなどに便宜を提供するだけでなく,規則や施行細則には盛り込み難い申し合わせ,内規,了解事項に属するものもここに記載しておきますので,後々,誤解のもとになりそうな事柄の参考にしてほしいと思います.
*なお、本指針は学会制度による研修の手引きとなります。専門医機構制度による研修の詳細については、こちらをクリックしてください。
2.専門医規則の解説
専門医制度関連各種委員会
専門医制度関連各種委員会の構成
平成26年6月より専門医制度関連各種委員会の構成が一部変更となりました.内容としては,理事会の下に,新たに専門医制度委員会,専門医資格認定委員会,研修プログラム委員会,また、引き続き,専門医試験委員会,学術委員会を設けることとなりました.
専門医制度委員会は,専門医資格認定委員会,研修プログラム委員会,専門医試験委員会を統括する委員会となります.そのため,それぞれの委員会で審議した内容を,さらに討議する役割を持ちます.また、専門医制度に関する関係規則の制定や改定なども行います.
専門医資格認定委員会は,専門医に関する各種の資格審査,つまり,専門医受験申請の資格,専門医資格の更新の審査を行います.また,認定後研修実績(後実績)の様々な単位数を決め,日本皮膚科学会以外の学術集会などの登録認定や単位数の決定等いわゆる研修集会の指定を行います.
研修プログラム委員会は,研修に関する各種の資格審査,つまり,主研修施設・研修施設の新規認定や変更などの審査,主研修施設・研修施設の更新の審査を行います.
専門医試験委員会は,認定試験を担当し,出題,採点,試験場運営の実務を行います.
学術委員会は,日皮会の学術活動について計画し,実施します.つまり,専門医資格取得のための教育研修を担当し,研修講習会の計画,認定前研修実績(以下,前実績と略します),研修内容の検討と改訂などを行います.
試験による専門医資格取得制度の開始
試験による専門医資格取得制度は,昭和62年4月1日から始まりました.この日付以後に会員になった医師が専門医の資格を得るには,すべてこの規則に従って研修を行い,単位をとり,資格を申請し,試験を受けなければなりません.
専門医の申請から登録まで
申請の資格
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医を取得するためには、次の申請資格を満たす必要があります.
(1)我が国の医師免許を持っていること.(2)5年間以上引き続いて日本皮膚科学会正会員であることを要します.なお,何かの事情で会員資格が途切れた時は,再び5年間の継続を必要としますので,ご注意ください.更に,(3)所定の研修実績を修了していること.(4)所定の前実績単位を取得していること(5)実際に皮膚科の診療に従事している方に限ります.
◆研修について
日本皮膚科学会の正会員として,皮膚科専門医研修を5年間行うことが必要です.この研修に関しては,日本皮膚科学会の指定を受けた主研修施設の皮膚科研修カリキュラムに従って,主研修施設および研修施設において責任指導医および指導医の指導のもとで5年以上の研修を行うことが必要です.もちろん5年を超えることは差支えなく,研修終了まで10年でも結構です.ただし,主研修施設での計1年以上の研修が必要ですので,研修に臨んでは先ず責任指導医に相談して研修計画を立てましょう.
また,日本皮膚科学会に入会した後の初期研修の期間は,皮膚科専門医研修期間に算定されます.たとえば,日本皮膚科学会に入会したタイミングが初期研修2年目であれば、そこから皮膚科専門医研修期間として算定になりますので,初期研修終了後に入会いただくよりも早く皮膚科専門医研修を終えることが可能です.ですが、初期研修の期間については前述の「主研修施設での計1年以上の研修」に含むことはできません。なお,一人医長の研修は2年間までは認められます.
ご自身の入会年月日を確認し,「受験申請の際に研修期間を満たさなかった」ということがないよう,余裕を持った研修計画を立ててください.
*2019年6月追記
専門医を取得するための研修期間は、原則としてフルタイム(週5日)勤務のみを算定しておりました.そのため、産休・育休などのライフイベントによる研修中断期間は算定できませんでしたが、2019年4月1日以降に取得した産休・育休期間については、最大6ヶ月間までを研修期間として算定することが出来るようになりました.なお、同期間については主研修施設の1年間の研修義務を短縮するものではありません.
*上記の産休・育休に関する補足
2019年4月1日以降に取得した、というのは「新規」で取得したということではなく、それ以降の産休・育休期間を指します.例えば、2019年3月1日から産休・育休を取得している場合、次のようになります.
例)2019年3月1日~2019年9月30日が産休・育休期間の場合
⇒2019年4月1日から2019年9月30日の期間が研修期間として算定
*2020年6月追記
専門医を取得するための研修期間について、下記の要件を満たしているのであれば非フルタイム勤務であっても研修期間として算定できるようになりました.これは,2018年4月からの非フルタイム勤務から算定可能となります.本遡及措置は専門医機構における研修プログラム制と合わせるための措置です.
非フルタイム勤務の場合、以下の表のとおり研修期間を算定できるものとする。
| 区分 | 「主研修施設」「研修施設等」で正規職員として勤務している時間 | 1ヶ月で取得できる研修期間 |
| 非フルタイム勤務 | 週26時間以上31時間未満 | 0.8ヶ月分 |
| 週21時間以上26時間未満 | 0.6ヶ月分 | |
| 週16時間以上21時間未満 | 0.4ヶ月分 | |
| 週16時間未満 | 0 |
上記の時間は週あたりの実労働時間ではなく、それぞれの施設で勤務時間として契約している時間です。
なお、「義務年限を有する医科大学卒業生、地域医療従事者(地域枠医師等)」に限り、下記の勤務時間であっても研修期間を算定できるものとする。
| 区分 | 「主研修施設」「研修施設等」で正規職員として勤務している時間 | 1ヶ月で取得できる研修期間 |
| 上記の特例枠 | 週8時間以上16時間未満 | 0.2ヶ月分 |
*上記の時間は週あたりの「皮膚科」実労働時間とする。
「研修内容」は出来るだけ具体的な方向付けを示すよう努力いたしました.これは医学の進歩に遅れないように,研修プログラム委員会で定期的に検討され,随時改訂されます.この「研修内容」は皮膚科専門医研修のいわばガイドラインであり,とくに認定前研修実績(前実績と略)においては,日本皮膚科学会が認定する主研修施設ごとに目標,方略および評価方法を示す皮膚科研修カリキュラムがありますので,それに従って研修してください.
主研修施設・研修施設と責任指導医・指導医
学会の掲げる「研修内容」を修得するには,それに相応しい研修環境と指導者が必要です.そのため日本皮膚科学会は「主研修施設」と「研修施設」の指定をいたします.
主研修施設の条件
主研修施設は特定機能病院あるいは医育機関の病院で皮膚科を標榜する独立診療科があることが必須条件です.指導医として認められるのは皮膚科専門医資格を有する皮膚科医で,その施設に複数名の指導医が常勤していることも主研修施設の条件で,その皮膚科の責任者が責任指導医です.
研修施設の条件
研修施設には皮膚科を標榜する独立診療科があることが必須条件です.これは専門医の研修ですので,同時に二つの制度の研修ができると思われる場合,例えば「皮膚泌尿器科」では認められません.また,内科,外科などの関連科が数科以上あることも条件です.また,研修施設は主研修施設と連携して研修を受け入れますので,該当する責任指導医と相談して研修施設での研修をしてください.前実績の終了証明は最終的に責任指導医にしていただきます.
責任指導医・指導医
皮膚科専門医研修では,常勤する日本皮膚科学会認定皮膚科専門医が指導医として研修の指導に当たることが必要です.主研修施設として届け出を行う際には、複数名の専門医が常勤することが必要で,1名を責任指導医と定め,もう1名の専門医を指導医として申請書に記入してください.責任指導医は,皮膚科専門医を1回以上更新している医師で,皮膚科の十分な業績と診療実績があり,研修で十分な指導力があることが必要です.これらの責任指導医・指導医と主研修施設とを併せて登録しますので,責任指導医や指導医が変わったら,直ちに再申請してください.一方,皮膚科専門医が常勤し,皮膚科を標榜する施設は,責任指導医の推薦を得て,当該皮膚科研修カリキュラムの研修施設として申請できます.認定されれば,指導医と研修施設とを併せて登録します.同様に,指導医が変わったら再申請してください.
◆責任指導医の業務:責任指導医は,日本皮膚科学会が示した研修ガイドラインを理解し,研修内容に基づき,その主研修施設と連携する研修施設で実施する皮膚科研修カリキュラムを作成して下さい.カリキュラムの内容としては,個々の行動目標をどのように達成するかの方略,個々の方略を行う時期や場所,その達成度を如何に評価するかなどを明記してください.足らないところは,他の科,他の施設や講習会などで補う旨,カリキュラムに組み込んでください.他科へのローテイトは計1年以内に限り,研修期間に算入されます.この場合の登録は不要で,提出された皮膚科研修カリキュラムに記載してくだされば結構です.このカリキュラムは施設指定のための条件ですので学会に届ける義務があります.この意味で,責任指導医が変われば指導方針も変わる筈ですので,新しい責任指導医が作成した皮膚科研修カリキュラムとともに再指定をうけてください.
◆指導医の任務:指導医は,責任指導医のもとで,示されている皮膚科研修カリキュラムに則して,皮膚科研修医を指導することが任務ですので,指導医は自らの専門医資格の更新を忘れないでください.
◆指定の申請:登録の申請は,施設の長(通常は病院長)が,(1)主研修施設・研修施設指定申請書と調査書に必要事項を記入して,(2)主研修施設では責任指導医の経歴・業績書と指導医の経歴一覧書,また,研修施設では指導医の経歴書,責任指導医からの推薦書と(3)主研修施設は責任指導医の作成した皮膚科研修カリキュラムとともに学会に提出してください.研修プログラム委員会、専門医制度委員会が審査の上,本会がその施設を指定し,主研修施設原簿ないし研修施設原簿に登録し,日本皮膚科学会認定専門医主研修施設ないし研修施設であるとして、主研修施設は翌年度4月1日付に、研修施設はその承認日付の研修施設認定証を交付します.
この登録は3年毎に更新することになっています.手続きを怠りますと,その施設での研修が無効になりますのでご注意ください.申請の時期は,毎年12月までを受付期間としています.
◆研修期間は5年以上です.
◆皮膚科研修医が研修施設を変更したり,指導医が途中で交替したりして,複数になった場合は,その旨を「研修修了証明書」に記載し,最後に当該皮膚科研修カリキュラムの責任指導医の署名が必要です.
単位取得の義務
専門医を志す方は,前実績として講習受講,学会発表,論文発表等について定められた総単位数,計150単位を取得してください.
講習会は,必須と選択とに分かれています.「必須」項目は規定を満たすように受講する義務があります.必須講習会は年度内3回行われます.但し各個人につき,「必須」として単位取得が可能なのは同一年度のうちの1回だけです.なお、余分に受講されることは差支えなく,選択講習会と同様に単位が加算されます.「選択」の受講義務はありません.足らざる所を補うように受講するのが望ましいことです.講習会出席の単位は計80単位を超えて加算出来ません.
学会発表は,自分で口演発表したものに限ります.
〔註〕ここで学会とは,原則として日本皮膚科学会に所属する学会を指し,加えて,後に述べます専門医更新手続きの項にある,登録された「研修集会」に含まれる学会のうち、後実績6単位以上認められているものを対象とします.厚生労働省,文部科学省等の班会議等の発表は単位とはなりません.
論文発表も申請者が単独著者又は筆頭著者であるものに限ります.内容が原則として皮膚科学に関するものであり,随筆,解説,書評等は見なされません.
〔註〕論文発表と認められるものは,1年間に2回以上発行し,1回につき発行部数600部以上で全国に広く頒布されている医学専門雑誌に掲載された皮膚科学およびその他の関連領域の論文,あるいはon-line journalであり、かつ、査読があるものと申し合わせておきます.また,厚生労働省,文部科学省等の調査研究班報告書,治験論文等は見なされません.なお,on-line journalにおいては,発行部数という概念がないため,「1回につき発行部数600部以上」という条件は除外されます.
これらの満たすべき単位数は次の通りです.
■単位数
| 講習会 | 必須 | 各10単位:30単位以上を義務とします. |
|---|---|---|
| 選択 | 各10単位.講習会の単位は計80単位を超えられません. | |
| 学会発表 | 各1回 | 5単位 |
| 論文発表 | 各1編 | 10単位.論文は3編(30単位)以上を義務とします. |
その他,理事会が前実績単位として別に認めたもの
総計150単位以上を必要とします.
〔註〕学会及び論文発表は単位加算に上限はありません.
申請手続き
以上の条件が満たされましたら,定められた期間内に下記の書類を事務局迄お送りください.その詳細は日皮会誌に掲載,告示します.
提出していただく書類は,(1)専門医認定試験受験申請書,(2)医師免許証(写),(3)研修修了証明書,(4)前実績記録(5)診療記録,(6)年間研修評価書です.
専門医資格認定委員会で書類審査され,条件を満たしているときは,専門医認定試験の受験資格が与えられます.なお,研修修了証明書は,責任指導医が皮膚科専門医認定試験を受験することが可能(研修目標に到達した)と判断したことを証明するものです.そのため、研修目標に達していないと判断する場合,研修修了証明書の発行がなされないことがあります.
専門医認定試験
研修目標に到達したかどうかを知るために,認定試験を行います.
試験は原則として臨床時に必要な問題を主とし,真面目に研修を行った者には容易な程度とし,いたずらに難解な問題は避けるように申し合わせております.出題範囲は,研修内容に準拠します.
認定,登録
試験に合格しますと専門医に認定されます.これは所定の手続きを済ませますと,同年10月1日付で専門医原簿に登録され,同日付の「専門医認定書」が交付されます.
次回資格認定期限は,平成15年度に専門医資格を新規に取得した場合,平成15年10月1日+5年6ヶ月=平成21年3月31日
となります.
更新について
専門医資格には期限があり,認定後5年たつと自然に消滅することになります.これを継続するためには,認定後研修実績(後実績と略します)として所定の単位を取得し、また、一定の診療に従事する必要があります.更新の詳しいことに関しては,4項(資格の更新)に述べてありますのでご参照ください.
専門医資格の喪失
次の場合には,専門医の資格がなくなり,専門医原簿から削除されます.
- 日本皮膚科学会会員の資格を失ったとき.
- 専門医の資格更新手続きを行わなかったとき.
- 専門医の資格更新が認められなかったとき.
- 専門医を辞退したとき.
- 医師の資格を喪失したとき.
- 専門医として相応しくない行為があったと理事会が認めたとき.
- 申請内容に重大な誤りがあったと理事会が認めたとき.
○専門医の資格を喪失した者が,再び資格を申請する場合の手続きは,更新ではなく,最初からの申請になります.
3.研修目標および研修内容の解説
日本皮膚科学会が示す「研修内容」につきましては,別に掲げてありますのでご参照ください.この研修内容は,学習者を主体として作成されています.指導にあたる指導医も熟読して,カリキュラムの作成と自己研修に利用してください.内容は,学習者が,何をどの程度に,どういう方法で学ぶかを示しており,学ぶべき内容を,「行動目標」として列記してあります.この目標を実現するための学習の方法を,具体的に例示し,これを「学習方略」といいます.これらの研修内容を修得したものが,専門医に相応しい資格と見なし,皮膚科学会の認定の基本条件となります.つまり,専門医の技量を具体的に示したものでもあります.そして,この内容を,現実に臨床の場で修得するには,最短5年は必要と判断いたしました.このように,この制度の全ては,この「研修目標と研修内容」を中心として考えが進められたものです.この「研修内容」はいわば全国で行われる皮膚科研修のガイドラインと考えてください.すなわち,個々の主研修施設では,この「研修内容」を達成するためにどのような方法で研修すれば良いか,あるいはどのように評価をするかを示す皮膚科研修カリキュラムを実情に合わせて,責任指導医の責任で作成します.また,連携する研修施設では,当該カリキュラムの一部を研修します.前実績では,主研修施設で少なくとも1年の研修を要します.
4.資格の更新の解説
○専門医は5年毎に資格の更新をしないと,その資格を失います.
○資格更新の条件として,引き続いて日本皮膚科学会会員であり,皮膚科診療に従事している方に限ります.
○資格取得または更新の後,5年間に所定の後実績単位数(100単位)を取得していることが必要です.また,平成28年度より専門医更新申請時に2.5年以上の皮膚科診療に従事していることの証明が必要となります.常勤であれば,当該施設(長)の証明書や診療スケジュール表(期間と時間が明記されているもの)が必要であり,非常勤であれば,上記資料のほか,日皮会代議員や主研修施設責任指導医の証明が必要となります.
○後実績単位は主として,登録学術集会,講習会等(これらを一括して研修集会と呼ぶことにします)への出席,論文や学会等の業績発表についてそれぞれの単位が定められています.
○更新に要する後実績単位数は総計,5年間で合わせて100単位です.但し,申請時当該年度中に満58歳以上に達する者に限り,更新に要する後実績単位数は80単位とします.
また,平成30年4月1日以降は,申請時当該年度中に満64歳以上70歳未満に該当する者は後実績単位数40単位を必要とすることとなります.
(1)研修集会への出席(後実績認定単位一覧表参照)
◆日本皮膚科学会主催の研修集会,1回につき10単位.但し3日にわたっても1回と計算してください.以下同様に扱ってください.
◆日本皮膚科学会総会,1回につき20単位,東部,東京,中部,西部の各支部主催の学術大会,1回につき12単位.
◆地区地方会,6単位.例えば,広島地方会,京滋集談会等の日皮会の各支部から委託される学会を指します.これらは年に数回各地方で開催されますので、出来るだけこれを利用されることを勧めます.
◆日本研究皮膚科学会,日本臨床皮膚科医会,日本小児皮膚科学会の総会,各10単位.上記以外の団体が主催する学術集会については,別表のとおりとなります.
◆日本皮膚科学会以外の団体が主催する,ここに定められていない学術集会(国際学会)については申請を受けて,専門医制度資格認定委員会で認定,登録し,単位数を決定いたします.プログラムなどを添えて申請してください.
(2)業績発表
◆学会発表は皮膚科関係学会の演者に限り5単位を申請できます,また、学会に参加した際の出席点もこれに加算出来ます.特別講演,教育講演などもこれに準じて加算します.主に皮膚科医以外の者が集まる場での講演は原則として加算の対象にはなりません.しかし,例えば「アレルギー学会」のシンポジウム「皮膚科領域のアレルギー疾患」の演者などは委員会に問い合わせてください.もし認められずに単位不足となりますと,専門医資格を失いかねませんので慎重にお運びください.
◆この制度による日本皮膚科学会主催の講習会講師には,講習会出席による単位数と同等の単位数となります.
◆論文は単独または筆頭著者に限り原著,著書,総説など1篇につき10単位です.前実績よりも範囲は広く,皮膚科専門誌,on-line journal,総合誌,著書で,内容が皮膚科およびその関連領域に限られていれば認められます.学会抄録,簡単な解説,啓発的文章,医療随筆,新聞の論説や解説などは単位となりません.医学関係以外の掲載誌のものは原則として認められません.研究班報告書も認められません.
○更新手続きの際のチェック
資格更新の審査は「専門医資格認定委員会」が担当します.審査の過程で必要に応じて,問い合わせることもあります.また,申告に重大な誤りがありますと資格更新が認められないばかりでなく,既に登録された資格を取り消される場合もありますので正確に記入してください.
○更新認定
審査が終わり,更新審査料をはじめ,所定の手続きを済ませますと,更新認定され翌年度4月1日付の「専門医認定書」が再交付されます.
次回資格更新期限は,平成15年度に専門医資格を更新した場合,
平成16年4月1日+5年
=平成21年3月31日となります.
○更新の特例
- 平成30年4月1日以降の申請時当該年度中に満70歳に達した後に,引き続き専門医資格を更新する方は,所定の更新手続申請書の提出と更新審査料の提出をもって申請可能です.但し,専門医資格修得後10年未満の場合は所定の専門医資格更新のための履修単位を必要とします.
- 病気,出産,海外留学などの,止むを得ない事情で更新できない場合は,専門医資格更新延期申請書および理由を証明出来る書類,例えば診断書等を添えて,専門医資格認定委員会に届けてください.単位を満たしていれば,更新の審議の対象になり,満たしていないときには更新期限の延期が許可されることがあります.ただ,余り常識を越えた遅れは認められませんので,委員会の決定に従ってください.
5.手数料の解説
この制度の運用には,相当の経費が掛かりますので,次の手数料を頂きます.
(1)書類審査料 22,000円
(2)試験受験料 33,000円
(3)資格認定料 33,000円
(4)資格更新審査料 22,000円
一旦納入された各種手数料は返却いたしませんのでご了承ください.
以上が日本皮膚科学会専門医制度の概要です.さらに具体的に知りたい方は,「日本皮膚科学会認定専門医規則」と「同施行細則」をご参照ください.