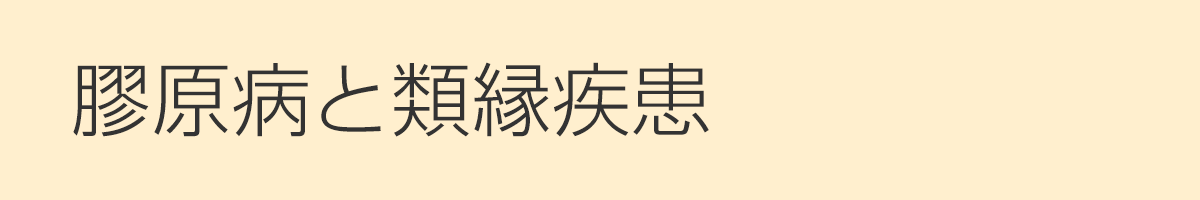Q9限局性強皮症の病変の広がりや活動性を調べるにはどのような検査が必要でしょうか?
限局性強皮症の病変が皮膚およびその下床の組織(脂肪組織、筋膜、筋肉、腱、骨・関節)にどの程度広がっているかを評価するには、造影MRIおよびドップラー超音波を行います。特に骨への病変の広がりも正確に評価できる点で、造影MRIが優れています。頭頸部に生じた限局性強皮症では脳病変を評価する必要がありますが、CT、MRI、脳波、SPECTが用いられます。
病気の活動性ですが、評価する基準として海外の学会では以下のような基準が提案されています。小児の限局性強皮症の患者さんを対象とした提案ですが、成人の患者さんにも適用できる内容です。
Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance (CARRA) が発表した小児限局性強皮症の疾患活動性評価基準
- 3カ月以内の新規病変の出現あるいは既存病変の拡大(医師が確認)
- 中等度から高度の紅斑あるいは紫色調変化
- 進行性の深部病変の存在(臨床所見、臨床写真、MRIあるいは超音波で確認)
のいずれか1つを満たすか、あるいは
- 3カ月以内の新規病変の出現あるいは既存病変の拡大(本人による報告、初診時のみ)
- 皮膚温上昇
- 淡い紅斑
- 病変部辺縁の中等度から高度の浸潤
- 頭髪、眉毛、睫毛の脱毛の進行(医師による確認)
- クレアチンキナーゼの上昇(限局性強皮症以外の病態によるものを除く)
- 活動性を示唆する病理組織所見
のうちいずれか2つ以上を満たす場合に活動性ありと判断する。
Li SC, et al. Arthritis Care Res. 2012; 64: 1175-1185.より引用、一部改変
病気の活動性を評価する上で重要な画像検査として、サーモグラフィー、超音波、造影MRIが挙げられます。上記基準の評価項目の1つとして「皮膚温上昇」がありますが、サーモグラフィーにより評価が可能です。超音波検査ではドップラー法による血流の評価が病変の炎症の程度をよく反映し、進行の予測因子となります。造影MRIでは、増強効果があれば活動性ありと判断します。上記の基準では血液検査所見としてクレアチンキナーゼ高値が含まれていますが、クレアチンキナーゼは筋肉が破壊されると上昇する検査値です。この異常を説明しうる限局性強皮症以外の病態がない場合は、筋膜あるいは筋肉に及ぶ活動性のある病変を反映している可能性が考えられます。