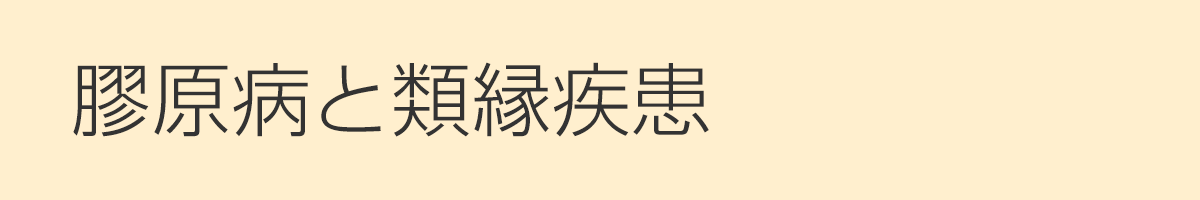Q16どのような内臓病変がみられますか?
全身性強皮症は多臓器疾患ですから、いろいろな内臓病変がおこる可能性があります。しかし、1人の患者さんが、すべての内臓病変をもつことは稀です。人によって合併する内臓病変やその程度が異なります。それでは、内臓病変を内臓別に説明しましょう。
まず、逆流性食道炎ですが、これは食道が硬くなって動きが悪くなった結果、胃酸が食道に逆流して生じるもので、胸やけ・胸のつかえる感じ・横になった時の逆流感が主症状です。逆流性食道炎は全身性強皮症の代表的な内臓病変の一つであり、典型的な全身性強皮症患者さんだけでなく、皮膚硬化が比較的軽い人にも多くみられる内臓病変です。また腸が硬くなって動きが悪くなると、便秘や下痢を繰り返したりします。腸がさらに硬くなって腸の動きがさらに悪くなると、強い腹痛や嘔吐などを生じる偽性イレウスと呼ばれる合併症を発症することがありますが、これは典型的な全身性強皮症患者さんで時にみられる症状です。
肺では肺線維症が代表的な病変です。これは肺が皮膚と同じように硬くなったもので、肺の下の方に生じます。進行すれば胸部レントゲンでもわかりますが、わずかな病変や早期の病変は胸部CTをとらないとわかりません(図12)。また肺の機能を調べる呼吸機能検査も必要です。その他、血液中で肺線維症と関連のあるKL-6やSP-Dも調べることが必要です。KL-6は肺線維症の重症度と関連しますので、この値が大きいと一般的に重症の肺線維症が起こる危険性があります。一方SP-Dは肺線維症の活動性と関連しますので、この値が高いと肺線維症の活動性が高く、現在悪化しつつあることを表しています。これらの検査は肺線維症があるのか、ないのか、というだけではなく、どの程度あるのか、さらに今進行しているのかを調べるために必要です。肺線維症は抗トポイソメラーゼ I抗体陽性で、比較的典型的な全身性強皮症患者さんに多くみられる症状です。
肺にはこれ以外に、肺の血管の血圧が高くなる肺高血圧症がみられることがあります。人間の体には2つの血圧があります。通常の血圧と肺の血圧です。通常の血圧は、120/80以下が至適血圧ですが、肺の血圧はそれよりずっと低くて25以下が正常です。肺高血圧症とは、肺の動脈が硬くなり内腔が狭くなって、肺の動脈の血圧が上昇する病気です。心臓の超音波検査で肺の血圧をある程度予測することができますが、間違いのない診断のためには心臓カテーテル検査が必要となります。肺高血圧症は抗セントロメア抗体陽性の全身性強皮症の患者さんに多く見られますが、欧米人に比べて日本人ではその発生頻度は少なく1%程度といわれています。
心臓についてですが、肺線維症や肺高血圧症がひどくなると心臓の働きが弱くなることがあります(心不全といいます)。また、心臓の筋肉が硬くなって、心臓の筋肉がきちんと動くための信号を送る伝導系に異常が生じて不整脈がおこることもあります。
肝臓では胆汁が流れる管が硬くなって、原発性胆汁性肝硬変と呼ばれる変化がおこることがあり、これは抗セントロメア抗体陽性で、比較的症状の軽い全身性強皮症患者さんに時にみられます。原発性胆汁性肝硬変と名前は恐ろしそうですが、特に自覚症状もなく、検査値の異常だけで治療を必要とすることもあまりありませんので不必要に心配しないで下さい。
欧米に比べてわが国では発症頻度は少ないですが、腎臓の血管が硬くなった結果、突然高血圧になり、頭痛、めまいなどがおこることがあります。これは強皮症腎クリーゼと呼ばれています。20年前までは命に関わる重篤な合併症でしたが、ACE阻害薬という高血圧のお薬によって治療が可能となりました。しかし治療が遅れると腎臓の機能が悪化して透析が必要となりますので、現在でも早く発見して、早く治療を開始することが極めて重要です。全身性強皮症の患者さんは毎日きちんと血圧を測定して、血圧が急に上がってくるようなときには直ぐに主治医の先生に相談するようにして下さい。強皮症腎クリーゼは抗RNAポリメラーゼ抗体をもった患者さんに多いことが知られていますので(10%程度)、この抗体を持っている患者さんは特に毎日に血圧の変化に注意して下さい。
また、全身性強皮症でも関節や筋肉に炎症がおこることがあります。
両側の黒い部分が肺であり、その中で両下方に白く濁っている部分が肺線維症。